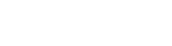今回は私たちが実際に改善した腰痛の具体的な例を一つご紹介します。最初に問い合わせがあったのは高校の柔道部の顧問の先生からでした。
全国優勝目指して逆スクワット
柔道部の顧問の先生からの問い合わせは、
「有能な生徒が腰痛で練習がまともにできなくなってしまったので、なんとかならないでしょうか」
というものでした。
内容は以下のようなものでした。
- 体幹を鍛えるために特殊な器具を足につけて、鉄棒に逆さまにぶら下がったまま逆スクワットをしていた
- 腰痛の部員が増えてきたため、腰痛のケアをするために、棒を使って大腰筋をグリグリと押していた
- それが原因か分からないが、有望な生徒が腰痛で練習に参加できなくなってしまって困っている
逆スクワットによって、大腰筋が筋拘縮して腰痛を引き起こしていたのは、間違い無いです。実際にこの生徒さんは大腰筋を緩めることによって腰痛が改善しました。
そもそも腰側の筋肉ではなく、大腰筋という腰椎(一部胸椎)から始まって鼠蹊部を通って太ももの骨に付いている、背骨よりも前側を通る筋肉が、なぜ腰痛に関係あるのか不思議に思う方もいるのではないでしょうか。
前屈をして痛みが出る腰痛と、腰を反らして痛みが出る腰痛は、痛みの原因となっている筋肉が違います。また、前屈をして痛みが出る腰痛は、腰を反らして痛みが出る腰痛よりも状態が悪いと言えます。
この辺りの詳しい話は
を読んでいただくとして、いずれの腰痛も「大腰筋」という筋肉が腰痛の根本原因になっています。
鉄棒に逆さまにぶら下がって逆スクワットをするということは、ただでさえ普通とは全く逆の大腰筋の使い方をし、その上非常に大きな負荷をかけることになりますので、大腰筋はそれらの負荷から守るために硬く強い筋拘縮になってしまっていたのです。
大腰筋を柔らかくしようと思ってやっていたことが逆効果に…
この生徒さんの施術は最初少し難航しました。大腰筋が予想していたよりも柔らかかったのです。ところが、その状態の筋拘縮を解除したところ、逆に硬くなってしまったのです。さらに根気強く筋拘縮を解除し続けているとと再び柔らかくなったのですが、今度は少しでも大腰筋に負荷がかけると再び硬い状態に戻ってしまうという現象が起きたのです。
通常の筋拘縮の筋肉は力が入ったままの状態ですので硬いはずです。筋肉の筋拘縮を解除すると力が抜けるので柔らかくなるのですが、この生徒さんのように筋肉が筋拘縮しているにも関わらず筋肉が柔らかいというのは、実は筋拘縮の末期なのです。
腰痛Labを読んでくださっている方であれば、もうお分かりかと思いますが、この筋拘縮の状態でも柔らかい状態というのが、私たちが「筋硬症(きんこうしょう)」と表現している状態です。
「筋硬症」という言葉を初めて聞いたという方は、こちらの記事を読んでみてください。
つまり、先ほどの現象は「筋硬症」→「筋拘縮」→「筋硬症」→「筋拘縮」を繰り返していたのです。
厳密に書くと「筋硬症」→「筋拘縮」→「見せかけだけの筋拘縮解除」→「負荷が加わる」→「筋拘縮」という流れになるのですが、何れにせよ、筋肉の筋拘縮が3段階目の「筋硬症」にまで進んでしまったために起きた現象でした。
さて、この生徒さんの大腰筋はどうして「筋硬症」の状態にまでなってしまったのでしょうか。
鍵となるのは、「大腰筋を柔らかくしようとして棒を使ってグリグリ」していたことです。おそらく、大腰筋の筋拘縮が1段階目の「筋攣縮」の状態であれば、棒でグリグリすると良い効果があった可能性が高いです。ところがこの生徒さんの大腰筋の筋拘縮は、逆スクワットをすることによって「より強い筋拘縮」の状態まで進行してしまっていたのです。この状態の筋肉に負荷や刺激を加え続けると、筋肉の筋拘縮はさらに進行して「筋硬症」になります。
良かれと思ってやっていた、大腰筋グリグリが逆効果になってしまった、ということです。
6回目の施術で完全復帰
これをひたすら、負荷をかけても筋拘縮しなくなるまで繰り返します。この生徒さんのケースであれば、1回目〜3回目の施術で全体的に筋拘縮をとりました。大腰筋などの「筋硬症」の箇所は通常のやり方では筋拘縮がとりきれませんので、筋拘縮が残っている状態です。「筋硬症」で筋拘縮の残っている箇所は、上記の負荷をかけて繰り返し緩める方法で筋拘縮を解除していきました。
高校生でまだ筋拘縮してからの期間が短いということと、栄養の状態がよかったこと、また大腰筋以外の筋拘縮が比較的軽かったことから、彼は6回目の施術で柔道の練習に復帰しても痛みが出ることがなくなりました。
後日談なのですが、実はこの生徒さんが所属していた柔道部、半分の部員が腰痛で危うく団体戦に出れなくなるところだったようです。何度か顧問の先生にお越しいただいて、大腰筋の緩め方とセルフ筋肉チューニングのやり方をお伝えし、大腰筋グリグリの代わりに筋拘縮を解除する方法を取り入れてもらいました。もちろん、逆スクワットも中止に。それ以降は腰痛で練習に参加できなくなるような大きなトラブル発生はしていないようです。